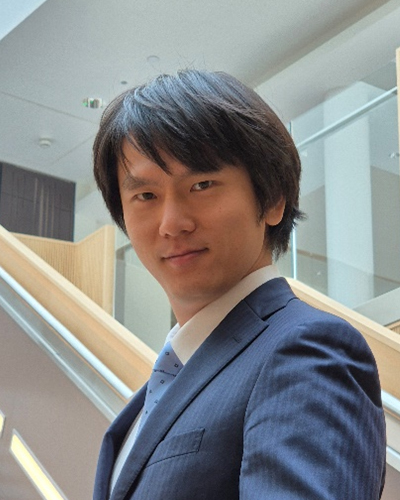
岸上 知志
2021~2024年度奨学生
オックスフォード大学 博士課程 化学学部
師からの試練と学び
坂口国際育英奨学財団の奨学生として、オックスフォード大学化学科博士課程に留学をさせていただいていた岸上知志と申します。今回は、私の博士号の学位取得に際して、これまでの坂口国際育英奨学財団および関係者の皆様からのご支援への感謝と留学全体の総括、そして今後への意気込みと抱負を述べたいと存じます。
最初に、先日ようやく論文化されることになった、ALS ( 筋萎縮性側索硬化症) の治療薬候補に関するドイツのマックスプランク研究所との共同研究について、生命科学の醍醐味や、国際共同研究の難しさについて触れながら振り返りたいと思います。本プロジェクトでは、これまでの医薬品とは一線を画す斬新な概念に基づいた治療薬開発という野心的な目的を追求するための非常に巨大なプロジェクトの中で、チームワークの重要性について学ぶところが多かったように感じています。こちらの研究に参加した研究者の総数は数十名以上に上り、その全員をとても把握し切れておりませんが、何名かのキーパーソンとは一緒に実験を実施したり、議論を交わすなどの機会があり、自らの専門知識の及ばない部分について限界を認めて謙虚に教えを乞うことは恥ではないと考えることができるようになりました。以前は自らの弱みを見せることへの躊躇や、議論の流れを遮りたくないという遠慮が邪魔をして、理解し切れない部分を質問せずにそのままにしてしまうところもあった自分でしたが、相手に対してもこちらの強みの領域の情報を元に提案をすると喜んでもらえることもあり、相互に長所と欠点を補い合うようなWin-Winの関係の構築について、少しは成長できたかなという気がしています。後述するように色々とマネジメントの面で確執もあった天才肌の指導教官からかけられた言葉の中でも「良い質問の定義とは自分が理解できていないことは何であるのかを極めて具体的かつ明確に伝えること(very specific aspect of notunderstanding)である」というコメントについては、今でも意識するようにしていますし、その定義に従った「良い質問」であれば今後も積極的に手を挙げてゆきたいと考えています。ALS についての病態の詳しい説明や我々の研究内容の詳細は省きますが、理解できないことをそのままにせず、未知の領域を探究し続ける努力と挑戦そして真剣な議論の繰り返しが、良い結果に繋がったように思います。
次に、上記のプロジェクトとは別のオックスフォード大学内で私がスタートさせ、途中にコロナ禍という危機を経験しながらも継続してきたタンパク質の複合体の細胞内での動的挙動を観測するためのフッ素を含有する非天然アミノ酸の新規合成と応用に関するテーマについても、技術的なところに加えて、人間関係の面で助けられた点や苦労したことが印象に残っています。指導を仰いだ2人の教授の方はどちらも常識に捉われない斬新な発想の持ち主で、研究者としての業績も傑出していました。しかし、前述した「良い質問」の定義を教えてくれた方はあまりにも天才的な頭脳を有しているがゆえに議論のレベルやスピード感を他者に合わせることができないことも多く、私自身も苦慮しました。
もう一方の指導教授は部下に対しての期待のレベルが高いことで常に過酷な要求をするところがあり、修士課程の学生として研究をスタートさせて間もない頃に化学科の他のラボの学生に彼の名前を伝えると、気の毒そうな顔でGood luckと言われたことをよく覚えています。ただし、やはり競争の厳しい世界で傑出した成果を出し続けてきた一流の人物だけあってその言葉には本質を鋭く抉る力と重みがあり、「お前は行動を起こす前から発生してもいない間題について心配しすぎだ。研究は不確実性の高い未知の領域への挑戦なのだから、事前に問題を予測することは難しい。実験の安全に関わるような事案は注意すべきだが、それ以外の問題は発生してから対処するしかない。」というコメントや、「助け合いは重要だが、他者に対して親切でありすぎるな。お前がお人好しすぎると他人はその親切心にタダ乗りするだけだ。(Don't be too nice to others because they may take advantage of your kindness.)」といったような言葉には、厳しい中にもこちらの生き方や将来へ警鐘を鳴らすような百戦錬磨の知謀を伺い知ることができました。そういった非常に要求レベルの高いボスをトップとしたグループであったがゆえに、同僚の学生とはお人好しになりすぎない範囲内で協力する関係を築くことができ、様々な面で本当に学びが多かったです。個々の事例を挙げるとキリがありませんが、自分と同年代の人物がこれほど成熱した判断力や人間性そして科学的な深い知識と技術力を兼ね備えることができるのかと、感銘すると同時に自己の成長へのモチベーションになりました。
研究活動に加えて、オックスフォード大学のアルティメットフリスビーチームや囲碁チームの活動にも積極的に参加し、どちらのチームでもライバルであるケンブリッジ大学との対抗戦のメンバーとしてVarsity match に出場することができました。私は決してアスリートとして一流とは言えず、囲碁の棋力もアマチュアの低段者レベルでしたが、身体能力やリーダーシップそしてAI による分析も活用した頭脳戦において卓越した世界各国の出身の仲間達から真摯に学びつつ、自分に出来る範囲でトレーニングや自主練習、そして創意工夫を重ね、幸運にも助けられて伝統ある対抗戦にOxford チームの一員として出場できたことは、研究の場だけでは得難いかけがえのない思い出と経験になりました。
最後に、上記のような実体験に基づく濃密で学びの多い機会を得ることができたのは、貴財団からのサポートがあってのことですので、関係者の皆様に心より深く御礼を申し上げたいと存じます。ただ、貴財団関係者をはじめとした様々な方々から期待をいただいて得た経験をどう活かすかによって、これまでの数年間において私が援助に値した人間であったかどうかが問われることになると考えますので、学位取得をゴールではなくスタートとして捉えて、様々な面で精進を続ける所存です。これからも頑張ります!

Exeter Collegeの中庭にて
