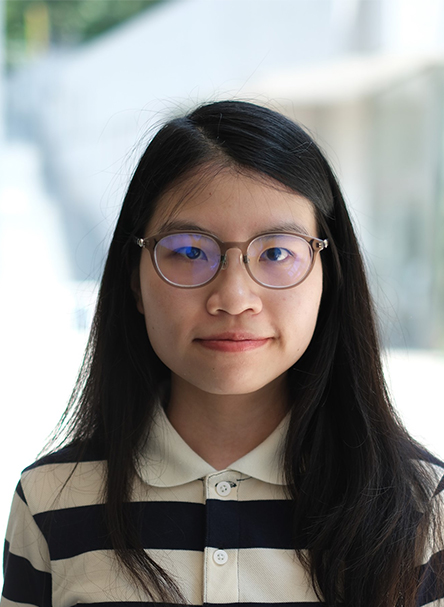
胡 佳融(フ ジャロン)
中国出身/2023~2024年度奨学生
上智大学 地球環境学研究科 博士後期課程
【第一部】危機を機会に変えた9年:留学生が見た日本の変革と私の未来
平成の最後の桜が舞い散る頃、私は日本へ留学し、大学の学部1年生として新たな一歩を踏み出しました。それから9年の歳月が流れ、学部・修士・博士へと進むうちに、日本社会は驚くほどの変化を遂げてきました。平成から令和へと時代が移り変わる中で、安倍晋三首相、菅義偉首相、岸田文雄首相が相次いで政権を担い、さらに石破茂氏が新たに内閣を組閣するまでの政治の動きを、私は留学生活の傍ら目の当たりにしてきました。長く続いたデフレから物価上昇へ移行する経済の変遷や、2022年の急激な日本円安による生活への影響など、私の留学生活はまさに社会変動の最前線に立っていたと感じています。一方で、新型コロナウイルスの流行は、日本だけでなく世界の価値観や働き方そのものを大きく揺さぶる出来事となりました。
経済と生活の変化:日本円安と物価高騰
私が留学を始めた当初の日本は、まだ現金社会の色合いが強く、コンビニや飲食店で支払うたびに小銭を持ち歩く毎日でした。アルバイト先でも現金決済が主流で、クレジットカードや電子マネーを使うお客さんは珍しく感じられたほどです。しかし、ここ数年でQRコード決済などのキャッシュレス手段が急速に普及し、レジの前でスマートフォンをかざす光景が当たり前になりました。私自身もポイント還元などのメリットを活用することで、留学生としての限られた予算を有効活用する工夫を学びました。
一方で、2019年の消費税増税の際には、アルバイト先のスーパーで駆け込み需要に追われ、その影響力を肌で感じました。そして2022年、日本円が急激に安くなり、輸入品の価格が跳ね上がると、生活必需品の値上がりを日々の買い物で痛感することとなりました。例えば、いつも購入していた日用品や食品の値段が気づかないうちに上がっており、買い控えや値引き品の活用が必要になるなど、節約を強いられる局面が増えていったのです。こうした経済環境の変化は、留学生にとって学業と生活の両立をいっそうシビアなものにしましたが、同時に予算管理の重要性を実体験として学ぶ貴重な機会でもありました。
社会と働き方の変化:労働力不足と高齢化・少子化
日本社会では、経済の変動だけでなく、労働力不足と高齢化・少子化が深刻な課題となっています。私がアルバイトをしていた飲食店やコンビニでは、外国人スタッフの割合が年々高まっているのを実感しました。店長は「若い日本人の応募が少ない」という現状に悩みつつも、多国籍なメンバーを積極的に採用し、彼らの言語力や適応力を高く評価していました。実際に私も、同僚として海外出身のスタッフと働きながら、多文化共生のメリットと課題を間近で見てきました。日本語のマニュアルが不十分であるケースや、接客用語の理解に時間がかかるなど、現場レベルではまだまだ改善の余地を感じる部分が多いのも事実です。
一方、高齢化社会の進展によって、各種店舗やサービス業では高齢者の店主や従業員が増えていると耳にすることもあります。特に小規模な商店では、ITやキャッシュレス決済などの新しい技術に対応する負担が大きく、労働力不足だけでなくデジタル化への戸惑いという問題も見受けられるようです。新型コロナウイルスのパンデミックによってリモートワークやオンライン授業が広がった一方で、操作や環境が整わない層との格差が拡大している点は、私自身の研究テーマである「持続可能なライフスタイル」の観点からも興味深く、社会全体でのサポート体制が必要だと感じています。
こうした日本社会の大きな変化の最中に留学生活を送れたことは、私の研究テーマである「持続可能なライフスタイル」の視点から、社会の実態を多角的に学ぶ絶好の機会となりました。労働力不足や高齢化・少子化といった構造的な課題が浮き彫りになる一方で、新しい働き方やデジタル技術の普及、多文化共生の必要性など、社会の変容が私たちの日々の行動や価値観に直接的な影響を与えていることを肌で感じています。
特に、人口動態の変化と環境意識の高まりが複雑に絡み合う今の状況は、私が研究する持続可能なライフスタイルにも直接的な影響を及ぼしていると感じています。若い世代や外国人材を積極的に取り入れる企業や自治体が増える一方で、高齢者やデジタル技術に不慣れな人々への配慮も不可欠となり、多様な人々が共に暮らし、働き、学ぶ仕組みづくりがますます重要になっています。こうした多文化共生と技術革新が同時に進む社会こそ、環境負荷の低減と社会的包摂を両立させるための新たな可能性を生み出す場であり、私自身も研究を通じて、その課題解決に貢献したいと考えています。こうした社会変化を実際に目の当たりにしながら、持続可能なライフスタイルや環境行動がどのように受容され、行動変容につながるのかを探究できたことは、私にとって大きな学びでした。社会構造が変わる今こそ、環境保護と社会福祉の両立を模索する絶好のタイミングであり、私自身も今後の研究を通じて、より良い未来のための実践的なアイデアを提案していきたいと考えています。
研究の変遷:大学生のゴミ分別行動から市民全般の持続可能なライフスタイルへ
私が取り組んできた研究テーマも、この9年間の社会の動きに合わせて少しずつ進化していきました。
学部時代(2016-2020年)
大学生のゴミ分別行動の変化と要因分析に着目し、とりわけ大学寮で暮らす留学生の国籍や文化的背景がごみ分別行動にどのような影響を及ぼすのかを考察しました。日本の厳格な分別ルールに対して、異文化圏の学生がどのように適応しているのかを探る中で、文化が行動に与える影響の大きさを実感しました。
修士時代(2020-2022年)
大学を卒業した2020年、新型コロナウイルスが世界を揺るがし、私の研究生活も大きく変化しました。オンライン授業や外出自粛という制限の中で、2022年に施行された「プラスチック資源循環促進法」に注目し、日本の既存のゴミ分別制度におけるプラスチック分別の深化に関する研究を進めました。特に、新しい政策が自治体や市民にどう受け入れられ、実践されていくのかを調べることで、政策が人々の行動を変えていく過程を追究しました。
博士時代(2022年~現在)
修士課程を修了後、私は研究のスケールをさらに広げ、「ごみ分別」にとどまらない「持続可能なライフスタイル」全体を対象とする博士研究に取り組んでいます。衣・食・住・移動など日常生活のあらゆる場面で、どのように持続可能性を実現できるのか、社会構造や政策との関連を含めて深く考察しています。
危機の中で学んだこと、そして未来へ
この9年間、日本は数多くの「危機」を経験してきました。パンデミックによる社会活動の制限、経済の不安定、さらには高齢化・少子化の加速や労働力不足など、課題は山積みです。しかし、「危機」という言葉が示すように、「危」には「危険」という意味がある一方で、「機」には「機会」という意味も含まれています。私は、この日本での留学生活を通じ、学部・修士・博士と研究を深めるうちに、危機を機会に変えるために必要な三つの鍵となる要素を学びました。
1. 多様性の受容
学部時代の研究では、外国人留学生が日本のゴミ分別ルールにどのように適応しているかを分析しました。結果、日本の厳格な分別ルールが外国人にとってわかりにくい面がある一方、自治体や大学が多言語対応を進めることで、多様な文化や言語背景を持つ人々の参加を促していることが分かりました。異なる視点を持つ人々が集まることで、新たなアイデアや価値観が生まれ、社会全体の課題解決力が高まることを、私はここで実感したのです。
2. 政策の柔軟な適応
修士課程へ進んだ2020年、新型コロナウイルスのパンデミックが世界を揺るがしました。オンライン授業や外出自粛が続く中、2022年に施行された「プラスチック資源循環促進法」を扱った研究に取り組んだのは、まさに政策が急速に変化するタイミングだったからです。既存のゴミ分別制度に新しい法律を掛け合わせる形で、自治体や企業、市民がどのように柔軟に対応していくのかを調査することで、政策の成否は、それを受け止める社会の適応力にかかっていると強く感じました。危機的状況においても、迅速に法や制度をアップデートし、それを社会全体で実行に移す力こそが、新たな可能性を生み出す鍵になるのだと思います。
3. 伝統的価値観の再解釈
博士課程に進んだ今、私はより広範な視点で持続可能なライフスタイルを探求しています。そこでは、日本古来の価値観、たとえば「もったいない」という精神が大きなヒントになると感じています。単に物を無駄にしないという考え方だけでなく、限りある資源を大切に扱い、人と環境が共存していくという世界観は、現代のサステナビリティにも通じる普遍的なメッセージを含んでいます。デジタル技術が発展し、多文化共生が進む一方で、こうした伝統的な価値観を見直し、現代社会に合わせて再解釈することが、危機を乗り越える新しい発想を生み出す糸口になるのではないでしょうか。
こうして振り返ると、私の留学生活はまさに日本社会の大きな変動と共に歩んできた時間だったと感じます。経済や働き方、政策、そして伝統的な価値観まで——それぞれが単独で存在するのではなく、互いに影響を与え合いながら、社会全体を形作っていることを実感しました。学部から修士、そして博士へと研究対象を広げる中で、私自身も少しずつ視点を広げ、複雑に変化する社会の中で「持続可能性」を実現するための多角的なアプローチを学ぶことができたと思います。
今後も、この経験を糧にしながら、新たな課題を「危機」ではなく「機会」としてとらえ、社会に貢献できる研究と行動を続けていきたいと考えています。
【第二部】奨学金によって果たせたこと、そして未来への展望
奨学金のご支援のおかげで得られた学術的成果と成長
奨学金のご支援のおかげで、経済的な負担が大幅に軽減され、アルバイトに割く時間を最小限に抑えることができました。そのおかげで、研究や学会発表、課外活動により集中することが可能となり、この2年間で大きく成長できたと感じています。
学術研究面
1. 国際学術誌への論文発表
2つの論文を国際ジャーナルに掲載し、そのうちの1本は第一著者として、環境学領域のトップジャーナルである Journal of Environmental Management
に発表されました。さらに、現在3本の論文を投稿中で、査読結果を待っています。
2. 学会参加・発表
2023年8月、青山学院大学での日本行動計量学会に参加(写真1)

(写真1)
2023年11月、中国・上海での国際学会(Global Cleaner Production Conference) でポスター発表(写真2)

(写真2)
注:私の研究室には若い女性研究者が多数在籍しており、そのことをとても誇りに思っています。
2025年2月、筑波大学東京キャンパスで日本計算社会科学会大会の口頭発表(写真3)

(写真3)
注:一緒に参加する予定だった研究室のメンバーたちがインフルエンザなどの理由で来られなかったため、発表当日は現地での写真撮影ができませんでした。この写真は、大会のライブ配信画面からスクリーンショットを撮影したものです。
3. 博士研究の進捗
2024年10月には博士中期口頭試問を無事に通過し、現在は最終的な博士論文の執筆段階に入っています。当初の予定では2025年9月に博士号取得を目指していましたが、論文投稿の遅れと日本の就職スケジュールの都合から、2026年4月まで修了を延ばす可能性があります。
当初の計画と変化、そして今後のキャリアビジョン
奨学金申請時には、博士課程修了後に母国へ戻り、大学教員として研究・教育に携わることを考えていました。しかし、中国国内の大学教員採用市場の激しい競争や、日本の大学の国際ランキングによる影響など、現実的な就職環境を再検討する中で、計画を修正せざるを得ない状況となりました。現在は、日本でポスドク研究員あるいは助教として経験を積み、その後タイミングを見て母国に戻る道を模索しています。日本の研究環境や実務経験を活かして、より実践的な視点と研究実績を持って帰国することで、祖国での大学教育や研究に一層貢献できると考えるようになったからです。
課外活動とライフスタイル面での充実
経済的安定に支えられ、研究以外の時間を有効に活用できたことも、大きな成長につながりました。
ボランティア活動
2024年3月に開催された東京マラソンで、外国語対応のボランティアとして参加しました。国際色豊かな大会運営の一端を担うことで、多文化共生への理解を深めたいと思っています。
スポーツ活動と健康管理
1. マラソン挑戦:2024年11月には人生初のハーフマラソン(21.0975㎞)を完走し、3時間でゴールすることができました。さらなるタイム短縮を目指して、2025年3月の渋谷女子10kmレースや6月の安曇野ハーフマラソンにも出場予定です。走ることで日々の研究疲れをリフレッシュし、身体を鍛える習慣を築いています。
2. フィギュアスケート:高校生の頃から憧れ、来日留学のきっかけにもなったフィギュアスケートにも継続的に取り組んでいます。研究とスポーツの両立は大変ですが、自分の好きなことを諦めずに続けることが、心身のバランスを保つ上でも大切だと実感しています。
最後に、奨学金に対する感謝と今後の抱負
坂口財団の皆様には、改めて深く感謝申し上げます。皆様のご支援がなければ、これほど研究と課外活動に集中することはできなかったでしょう。おかげさまで、国際誌への論文掲載や学会発表、さらに博士研究の進展といった学術的成果を得ることができただけでなく、スポーツやボランティア活動を通じた人間的な成長も果たすことができました。
今後は博士号取得を目指すとともに、日本でのポスドクや助教としてのキャリアに挑戦し、実践的な研究経験を積んだうえで、いずれ母国に戻り大学教育や研究に貢献したいと考えています。危機を機会の種に変える思考法を胸に、持続可能な未来を築くための研究と国際的な連携を推進していく所存です。これからもご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
