
陳 露文(チン ロブン)
中国出身/2024~2025年度奨学生
日本女子大学 人間社会研究科 博士後期課程
① 日本に来て最も変化したこと
日本に来る前、私は人生とは決められたレールの上を進むものだと考えていた。大学を卒業し、就職し、結婚し、子供を持つ——そうした一般的なライフコースを辿ることが当たり前であり、それ以外の道は「失敗」と見なされるものだと思っていた。しかし、日本での生活を通じて、その考えが大きく変わった。
日本語学校では、さまざまな人生経験を持つ人々と出会った。香港の名門大学に合格したにもかかわらず、自分の専門が合わないと感じ、退学して日本で学び直すことを選んだ香港の留学生。40歳を過ぎても結婚せず、一人で日本に来て新しい生活を楽しんでいる上海人女性。さらには、65歳を超えてから日本語を学ぶために来日し、しかも一年でN1を突破した韓国人おばあちゃんもいた。彼らと接する中で、人生には決まった正解などなく、自分の意志で選択する勇気こそが大切なのだと気づいた。他人の期待に縛られるのではなく、「自分の人生は自分で決めるものだ」という価値観が芽生えた。
また、早稲田大学の修士課程で出会った社会人学生や、定年退職後に修士号取得を目指す人々との交流を通じて、年齢や社会的な立場に関係なく、学び続けることの意味を深く考えるようになった。こうした出会いがあったからこそ、「常識」に縛られる必要はなく、自分のペースで生きてよいのだと思えるようになった。そして私は、ただ安定したキャリアを築くためではなく、本当に学びたいことを学ぶために、早稲田大学を退学し、日本女子大学へ進学するという決断をした。この選択は両親の強い反対を招いたが、私は初めて「自分のために生きる」という実感を得ることができた。
さらに、日本での生活を続ける中で、「日本にいるからといって、日本人のように生きなければならないわけではない」という考え方も持つようになった。来日当初は、日本人のように振る舞おうと努力し、外見や話し方まで意識的に日本に溶け込もうとしていた。しかし、今の私はそういったことを気にしなくなった。例えば、一人で出かける際に無理に化粧をすることはなく、化粧をしていないからといってマスクで顔を隠すこともしない。「社会の習慣」に無理に従うのではなく、自分が納得できるものを選び、納得できないことには流されない。日本での生活を通じて、自分の価値観に忠実であることの大切さを学んだ。
また、博士課程の進め方に対する考え方も変わった。以前の私は、博士課程はできるだけ早く修了し、日本の大学で就職しなければならないと考えていた。しかし、今はその考え方を手放した。博士号を何年で取得すべきかに決まったルールはなく、自分のペースで進めても良いのだと気づいた。私の先輩の中には、3年間博士課程を進めた後、一度休学し、出産・育児・仕事を経て、子どもが学校に入った後に博士課程に復帰した人もいる。以前の私は、人生は一本道であり、一度進んだら戻れないものだと思っていた。しかし、今の私は、人生にはいくらでも「戻れる道」があると理解できるようになった。
② 坂口国際育英財団の奨学金によって果たせたこと
日本女子大学への進学に際し、私は両親の援助を一切受けられなくなった。そのため、学費や生活費をどう賄うかが最大の課題となった。しかし、幸運にも坂口国際育英財団の奨学金を受給することができ、それによって私の人生は大きく変わった。
まず、この奨学金によって2年間の学費と家賃を賄うことができた。これは単に経済的な負担を軽減するだけでなく、「生きるためにアルバイトをしなければならない」というプレッシャーから私を解放してくれた。もし奨学金がなければ、私は学費や生活費を稼ぐために長時間のアルバイトをせざるを得ず、研究に十分な時間を割くことは難しかっただろう。アルバイトの時間が増えれば増えるほど、当然ながら研究や勉強の時間は減り、精神的な余裕もなくなっていく。多くの博士課程の留学生が、経済的な理由で研究時間を削らざるを得ない状況に直面している。私もまた、奨学金がなければ同じ状況に陥り、日々の生活に追われるだけの時間を過ごしていたかもしれない。
しかし、奨学金を受けたことで、私は研究に集中できるだけでなく、将来についてじっくりと考える時間を得ることができた。「博士号を取得すること」が目的ではなく、「私は最終的に何をしたいのか」「私は社会にどのような形で貢献できるのか」という、より本質的な問いに向き合う機会を得た。そして、私は単なる研究者としてではなく、社会に貢献できる存在になりたいと考えるようになった。
具体的には、日本に来たばかりで不安を抱えている留学生の支援、日本語が不自由なために社会で孤立してしまう在日中国人女性の支援に携わりたいと考えている。日本の大学のシステムや生活に関する情報を整理し、定期的にSNSで留学生向けに発信することを、去年から始めたのである。アルバイトの経験から、教授との付き合い方、学校を選びかた、自分の専門である教育学のおすすめの本など、多くの情報をシェアしている。そして知らない留学生同士からもらった「本当に助かった!」「ありがとう」「おかげで理想校に受かった」「もっとシェアしてほしい」の声が、私のやりがいになったのである。
坂口財団の奨学金がなければ、私はこうしたことを考える時間も、行動を起こす余裕もなかっただろう。学費や生活費を稼ぐためにアルバイトを優先せざるを得ず、自分の将来について深く考える機会を持つことすら難しかったかもしれない。しかし、奨学金のおかげで、私は「自分の人生をどう生きるのか」「自分は何を大切にしたいのか」を真剣に考えることができた。そして、その答えとして、「博士号を取得すること」だけではなく、「社会に何かしらの形で貢献すること」を目指すようになった。
坂口国際育英財団の奨学金は、単なる研究に集中できる経済的支援ではなく、私に「自分の人生を主体的に選択する機会」を与えてくれた。この支援を受けたことで、私はより自由に、そしてより深く、自分の人生を考え、歩んでいくことができるようになった。他人の期待に応えるためではなく、自分のために生きること——それこそが、私が日本で学んだ最も大切なことであり、そして坂口国際育英財団があったからこそ叶えたことである。

写真1:2022年、早稲田大学修士課程を卒業した

写真2:2023年、日本女子大学に入学した
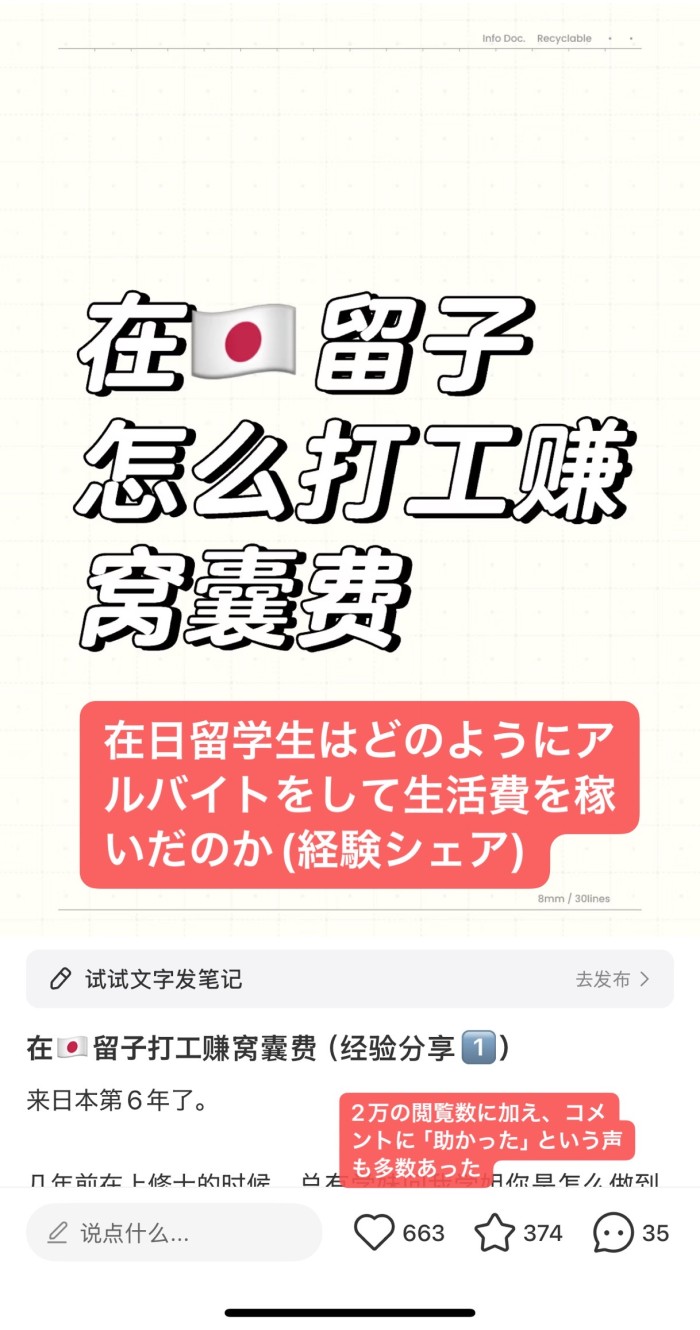
写真3:中国のSNSで自分のアルバイト経験をシェアし、多くのいいねとコメントをもらった
