
アリアドネ・ジュールダン・ファイオン
ブラジル出身/2024~2025年度奨学生
東京外国語大学 総合国際学研究科 博士前期課程
気候不安と環境保護の未来へ
2025年、日本に移住してから5年が経とうとしています。高校卒業後すぐ、18歳でこの国に来ました。自分の「大人としてのリテラシー」はすべて日本で培われたと言ってもいいでしょう。賃貸契約の結び方、銀行口座の開設、携帯電話の契約の仕方を学びました。敬語を含む言語的な階層構造を理解し、職場での振る舞い方を覚えました。学部を卒業し、修士課程に進学しました。数え切れないほどのカルチャーショックを受け、それを乗り越えながら、日本での新しい生活を慣れるようになりました。
それでも、毎年休暇の時期に、家族と友達に会うために帰国する機会を作っています。しかし、ブラジルに戻るたび、少しずつ自国の生き方を忘れつつあることに気づきます。年を重ね、成熟するにつれ、この世界がどれほど不公平であるかも痛感するようになりました。そして、私は常に不安な状態に順応しなければなりません。経済的不安、家を出て無事に帰れるかわからない不安、帰宅したときに水や電気が使えるかどうかの不安などです。
帰国する2月には、日本では冬は耐えがたい寒さですが、ブラジルでは真夏の暑さとなります。私はリオデジャネイロ出身で、帰国するとまず海へ行き、ココナッツウォーターを飲みます。久しぶりに太陽を浴び、夏の暑さを体に染み込ませ、ビタミンDを補給します。しかし、18年間リオで暮らしていたとき、夏は最も嫌いな季節でした。私の学校にはエアコンがなく、毎日乗っていたバスにも冷房ありませんでした。私は市の郊外に住んでおり、海へ行くのも簡単ではありませんでした。今こうして夏を楽しめることは、私にとっては特権ですが、大多数のブラジル人にとってはそうではありません。
2025年にブラジルへ行った際、「気候不安」という言葉を初めて耳にしました。2月の第3週、最高気温は40℃を超え、一部の地域では体感温度が60℃に達しました。実際、リオの観光地を除くと、街にはほとんど緑がありません。本来は熱帯雨林に覆われた地域ですが、無秩序な都市開発によりコンクリートの建物が増え、ヒートアイランド現象を引き起こしています。そして、最も影響を受けるのは貧困層の人々です。東京のベッドタウンのように、多くの人々が都心へ通勤しなければならず、老朽化した冷房のない満員電車やバスに頼るしかありません。日焼け止めは日光対策の一つですが、高価で手の届かないものです。暑さは短期・長期的影響を及ぼします。
さらに、2024年のリオグランデ・ド・スル州(ブラジルの一番南にある州)の災害以来、全国で洪水が頻発するようになりました。今月初め、私の母はブラジル北東部のレシフェで講演を行う予定でした。しかし、夏の大雨による地滑りと洪水のため、イベントは中止となり、オンラインで発表することになりました。その豪雨で7人が亡くなりました。そして昨日、2月19日、リオデジャネイロに隣接するサンパウロ州では豪雨による洪水で道路が冠水し、車内で2人が溺死しました。
経済的不安、治安の問題、基本的なインフラの欠如に加え、ブラジル人は気候不安を日常的に抱えています。そして、それは特に貧困層にとって深刻です。リオの暑さと聞いて思い浮かべるのは、コパカバーナビーチやキリスト像、カーニバルかもしれません。しかし、現実には、緑の少ない街並み、コンクリートの建物、そして熱を蓄える金属屋根が広がっています。

リオデジャネイロの郊外
ここで、日本での生活に話を戻しましょう。日本は寒さが厳しいですが、夏も非常に暑い国です。そして、日本人はこの四季の変化を祭りや伝統を通じて楽しんでいます。日本の自然との関わり方は美しく、私も公園でのランニングや登山を学びました。日本での「気候不安」に最も近いものがあるとすれば、それは地震や台風活動への恐れだと思います。しかし、それらに対する備えは非常に整っています。英語教師として働いていたとき、子供たちに最初に教えるのは、地震時の避難ルートや対応手順でした。それが安心感を与えてくれます。
日本で学んだのは、災害から身を守る方法があるということです。地震のような制御不能な自然現象に対しても、リスクを最小限に抑えるためのシステムが築かれています。ならば、人間が引き起こした問題(気候変動や都市計画の失敗)も、解決可能なはずではないでしょうか?この危機感から、私は人間と自然の関係をテーマに修士研究を進めることにしました。日本での経験と、母国で感じる心配の両方がその動機です。
持続可能な環境との関係を築こうとしている人々と出会いました。リオデジャネイロ近郊の小さな町、カジミロ・デ・アブレウでは、地域の人々が何十年前から環境との共生を目指しています。私はこの取り組みについて、リオで生活していた頃は知りませんでした。しかし、2024年に東京で訪れた環境保全プロジェクトに共鳴するものを探していたとき、この町の農業サイトにある「アグロフォレストリー・システム(SAF)」に辿り着きました。そこで、プロジェクトの責任者である農学者Lidiane Limaさんに連絡を取り、2025年初めに現地を訪れることになりました。
カジミロ・デ・アブレウへ向かう途中、私たちはリオを離れ、田舎へと続く道を進みました。景色に見えるのは、牧草地とわずかな木々、そして数多くの牛たちです。幼い頃の私は、これがこの地域本来の風景だと思っていました。しかし、実際には、それは農業開発の結果であり、本来の植生は熱帯雨林なのです。そもそも牛は植民地時代以前のブラジルには存在しませんでした。リオの本来の姿は、気温を調整する役割を持つ密林の森なのです。
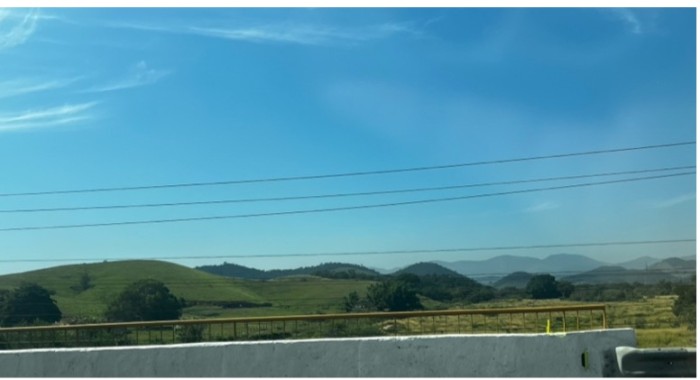
カジミロ・デ・アブレウへの道
農業サイトに到着すると、LidianeさんとチームがSAFを案内してくれました。2003年に森林再生の取り組みが始まったこの広大な敷地は、見渡す限り緑が広がっています。気温が非常に高い日でしたが、森に足を踏み入れた途端、気温が下がり、快適に歩きまわることができました。地域の在来樹木に加え、このSAFは、花粉媒介者、果樹、小さな菜園、水路を組み合わせた多様な生態系を形成しています。プロジェクトでは、養殖用の天然池も整備されていました。私たちは、カカオ、コーヒー、バナナ、アサイー、グアバ、パッションフルーツなど、さまざまな作物を見えました。これらの食材はすべて、現地で働くプロジェクトの参加者たちの食事として使用されているそうです。
このプロジェクトで最も関心を持ったのは、その参加者でした。この取り組みの一環として、「若手有機農家・造園家」(Jovem Agricultor Orgânico e Paisagista mirim)というプログラムがあり、住民の中の若者を対象に持続可能な農業技術を学ぶ機会を提供しています。森林破壊や若者の都市流出が進むこの地域で、プロジェクトは若者たちが故郷に留まりながら、環境を破壊することなく収入を得られる手段を提供しています。今年の応募者は100人を超えたそうです。

アグロフォレストリー・システム(SAF)
このような若者たちの関心の高まりが、リオデジャネイロが気候危機を克服できる可能性を示していると思います。もちろん、小規模な取り組みだけでは都市全体を救うことはできません。地方自治体とこうした草の根の活動との関係には、さまざまな課題が存在します。しかし、私の研究を通じて、このようなプロジェクトに直接関わる人々(例えば、SAFで働き、自然と調和した生活を目指すカジミロ・デ・アブレウの住民たち)の声を伝えることができればと願っています。
