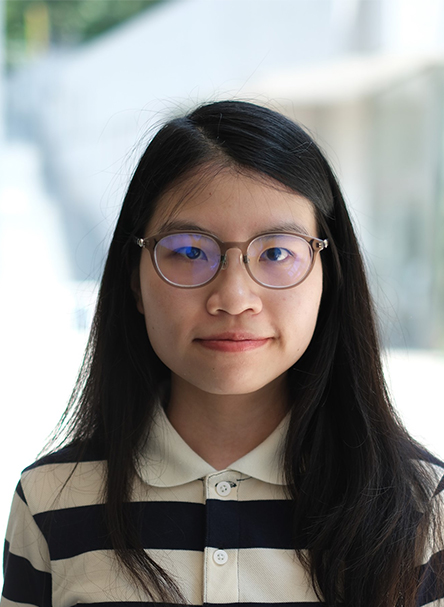
胡 佳融(フ ジャロン)
中国出身/2023~2024年度奨学生
上智大学 地球環境学研究科 博士後期課程
生成AIと学びの未来:利便性の影と思考力の試練
このエッセイは、最近私が学術論文の査読活動を通じて得たインスピレーションから生まれたものだ。ある日、私は査読者として、高等教育におけるAIの導入というテーマの論文に向き合っていった。その内容を読み進めるうちに、生成AIがもたらす可能性と、それに伴う課題について深く考えざるを得なかった。それは私にとって新たな視点を与え、この技術が私たちの学びと研究の現場にどのように関与しうるか、より深く考察する必要性を感じるきっかけとなった。
生成AI、特にChatGPTなどの大規模言語モデルは、近年急速に高等教育および学術分野に影響を与え始めている。本エッセイでは、生成AIの利点と課題の両面から、学術分野におけるその可能性と影響について考察する。生成AIは確かに多くの利便性をもたらすが、その利用には慎重さも求められる。
まず、生成AIの利点について述べる。学術分野において、生成AIは高等教育における個別化学習の促進に寄与している。例えば、ChatGPTは学生のレベルに応じたカスタマイズされた教材を提供することが可能で、授業中に理解できなかった内容を補足する手助けをすることができる。さらに、教員にとっても生成AIは、課題の採点や教材の準備といった時間のかかるタスクを自動化することで、より創造的な教育活動に集中する余裕を生み出す。学術分野においても、生成AIは文献のレビューやアイデアの整理に役立つツールだ。多くの研究者は、膨大な文献を調査する際、生成AIを用いて効率的に関連情報を抽出することが可能だ。また、非英語圏の研究者にとって、AIは英語の文章作成や編集を支援する強力なツールとなる。このように、生成AIは学術活動において多大な効率化をもたらしていることは否定できない。
しかし、生成AIの利用にはいくつかの深刻な課題も存在する。まず第一に、学術的な倫理や誠実性に関する問題だ。生成AIを利用して文章を作成する際、どこまでが自身のオリジナルな考えで、どこからがAIによる生成物であるのか、その境界が曖昧になるリスクがある。特に、学術論文の執筆において、AIの力を借りすぎることは、独創性や研究者の思考力を損なう可能性があり、学術界における信頼を揺るがす懸念が生じている。さらに、生成AIの登場により、国際的な学術論文の投稿が以前にも増して難しくなっていると感じる。まず、AIの助けを借りて研究者が論文を完成させるまでの時間が大幅に短縮されたため、投稿される論文の数は増加しているが、その質は以前ほど高くないことも多い。これは私が査読者として特に実感しているところだ。加えて、論文投稿数の増加により、編集者や査読者の負担が増し、投稿から返答を得るまでの期間が非常に長くなるケースが増えている。一つの論文が半年、一年といった長期間返答が得られないこともあり、そのために多くの研究計画が狂ってしまうことがある。
また、高等教育の現場においても同様の懸念が存在する。生成AIが提供する答えはしばしば表面的であり、学生が深く考える機会を奪う可能性がある。例えば、最近私が講義を担当した際、ますます多くの学生がAIを利用して授業に参加するようになっている。同時通訳を使用したり、難解な概念を検索したりと、AIを活用すること自体は学習の一助になるかもしれないが、その結果、教室内の効率が下がることに気付いた。特に、授業中の教室が非常に「静か」になってしまう点が問題だ。この「静かさ」とは、学生たちが自発的に質問したり、議論したりすることが少なくなったことを指している。私自身が学生時代に経験した、活発な議論が飛び交う教室とは大きく異なる。さらに、授業の終わりに学生たちに疑問点や質問があるか尋ねても、やはり反応は“静か”だ。このような状況では、学生の学習への積極性や、思考する力がAIの過度な利用によって制限されてしまう可能性があると感じている。例えば、AIに依存して課題を解決することで、学生が自分で試行錯誤するプロセスを経験することなく、簡単に解答を得ることができてしまう。このような状況が続くと、学生の批判的思考力や問題解決能力が十分に育たない恐れがある。
以上のように、生成AIには学術分野において多くの可能性を秘めているが、その利用にはいくつかの課題とリスクが伴う。これらの利点と課題を十分に理解し、生成AIを適切に活用することが求められる。教育者や研究者は、AIをただの便利なツールとして使うのではなく、それが学生や自身の成長にどのような影響を与えるかを常に考慮する必要がある。生成AIは強力なツールだが、その使い方次第で私たちの思考力や創造性がどのように変わってしまうのか、私たちは今こそ考えるべきだろう。
